第26回全日本教育工学全国大会・高知大会(2000.10.27)
普通科高校における1年次からの情報教育
- むずかしいけれどがんばる -
広 瀬 徹
<概略> 本校では、1年次必修1単位の「情報基礎」、2年次3単位の情報類型必修の「情報処理」が設けられています。1年次で実施した授業は、コンピュータグラフィック・ワープロ・エクセル表計算入門、ホームページ作成、Gifアニメーション作成です。2年次では、エクセル中級、フリーウェアを使った3D動画ムービー、Midiオリジナル作曲(7月まで)を実施しました。
これらについての授業内容、生徒の反応、今後の課題について報告します。
<キーワード> 情報教育、情報基礎、教育課程、カリキュラム、類型選択、普通科高校での必修
1.<学びたい>を育てる新課程カリキュラムへ
尼崎市の公立普通科高校として、地域の公立中学校からの進学者を迎える本校は、ここ10年ほど大きな変化を迎えました。
1994年に設置された「将来構想検討委員会(ビジョン委員会)」は、その変化を「基礎学力低下」「学習意欲低下」「基本的生活習慣の乱れ」による「原級留置・中途退学の増加」「問題行動の続発」ととらえ、同時に「進路の多様化」「生徒の興味・関心の多様化」が進んでいることを、具体的数字とともに、全職員・保護者に示しました。
その中で学校改革に取り組むことが合意され、カリキュラムの改訂と学習条件整備が討議されました。
1998年以降、「制服改訂」、「朝の読書時間設定10分」、「食堂の大幅改修」などの条件整備が取り組まれました。
しかし依然として、留級・中途退学率は下がらず、合わせて8%に近いものでした。長年つちかってきた県尼の大切なことがら、生徒の自主活動・教師生徒間の親密さが息づいているとはいえ、なんとしてもくい止めたい一番の事柄でした。
やはり授業です。毎日の授業の在り方を変えるしかないとカリキュラムの改訂の討議が続き、1998年10月、新課程(1)が決定されました。
その概要は、
(1)1年次では共通履修科目のみとし、すべての科目をバランス良く学習する。特に、国・数・英の3教料については、少人数指導を導入し、基礎・基本の徹底を図る。
(2)情報化時代を迎える社会の変化に相応して、1年次に週1時間の「情報基礎」を全員が学習する。
(3)2年次からの類型については、従来は「就職試験に通るための就職コース」「4年生理工系大学進学を対象にした理系コース」「文系進学、専門学校進学、その他もろもろの進路を含んだ文系コース」という3類型コース選択をやめることとする。そして、多様化した生徒の興味・関心に応じた教育課程を編成する、
①国語・地歴・公民を中心に学ぶ「人文社会類型」
②数学・理料を中心に学ぶ「自然科学類型」
③英語・地歴・公民を中心に学ぶ「国際文化類型」
④情報・商業を中心に学ぶ「情報科学類型」
の4類型に分ける。
それぞれの類型で、進学、就職、専門学校等の進路を実現する。
(4)選択科目を、2年次8時間、3年次20時間と大幅に増やす。類型に応じた科目を工夫すると共に総合化、国際化、福祉社会に応じた「地域尼崎学」「ハングル」「中国語」「ボランティア実践」などの 新科目を準備する。
という、<学びたい>を育てたいとする新課程です。
2.1年次必修「情報基礎」が始まった
1999年4月、新課程最初の学年54回生入学。週1時間ですが、1年全員の必須として「情報基礎」が、2名の複数担当で始まりました。
最初はマウスのクリック練習のための「マウス体操」のプログラム、「もぐらたたき」「めだかすくい」「こそだて」です。「わー、逃がした。」「つかまえた。」と大にぎわいです。
全員必修としたときの課題のひとつは、「学習規律の定着」です。勝手に画面をいじって袋小路にはいらない、先生の指示を聞き落とさない、の2つを「しつけ教育」としてやらねばなりません。国中に蔓延している自己中心的ふるまいは、生徒たちにも色濃く影を落としています。聞いていなくても「オトナ」はなんとかしてくれる、実際してくれたのだと思います。時には面倒を見ないことで、自分に不利益であることを体感させるしかありません。
1学期前半、「Windows入門」として「四季を描く」を「ペイント」を使ってコンピュータグラフィックに取り組みました。
中間考査までたった4,5時間しかありません。それでも320名の生徒たちはたくさんのCGを描きました。清新な作品がたくさん出来上がりました。後述する「県尼ホームページ」の「授業」に作品を掲載していますのでぜひ見て下さい。
「自己を表現する手だてとしてコンピュータがあること」、細かい操作技術やコンピュータの仕組みの覚え込みではなく、このことを1年間のテーマとして進めていますが、第1歩としていい教材でした。
1学期後半は、「ワープロ入門」です。
2時間ほど、サイズやフォント、カラー、文字飾り、罫線、イラスト貼り付けを学習して、さあ、「おとうさんやおかあさんのための旅行プラン」を作ろうとよびかけます。国内外の旅行パンフレットを100種ほど用意して、自由に選ばせます。「おとうさんやおかあさんのいないおうちあるとおもうけど、2倍よろこんでもらうためのプランを作ろう。1枚だけカラープリントしますから、手渡してください。」と話します。直後こんな感想に出会えました。
「母を想って作ったものだから、最中は母の照れくさそうに笑う姿が思い浮かんできて、すごくわたしもてれくさかったけど楽しかった。きっと家族を心から嫌いな子なんていないから、家族のために何かを考える、ていうのは良い事だと想った。いつか旅行は実現させたい。授業はすごく楽しかった。」
この授業、やって良かったと思います。
この夏休み、懸案だったインターネット接続が県立教育研修所を仲立ちとして生徒機40台にも可能となりました。生徒たちにインターネットの醍醐味を味わせることができます。
2学期前半は急遽、「インターネット入門 情報の受信と発信」HTML文書の学習としました。
さっそくインターネット接続します。
リンク集を作っておくのですが、わざと英語版だけにしておきます。パリ、ニューヨーク、モスクワ、香港、エジプト、すべて英語であることを見せ、英語版でなければ世界には通用しないことを伝え、県尼や尼崎市や日本、日本の若者を紹介する英語のホームページを作ろうとよびかけ、作成しました。どうしてものときはローマ字で良いこととしました。
「メモ帳」に直接<H1>Introduction</H1>などのタグを書きながらそれを「ブラウザ」で「更新」しながら見る、という方法を使いました。全角・半角の混同がないぶんやすやすとページが表示されていきます。1行1行書いていくことでホームページが出来上がっていくプログラム的側面がきちんととらえられたようです。
2学期後半はいよいよ「表計算入門 エクセルを学ぶ」です。コンピュータが計算機と言われるゆえんがよく分かるところです。
尼崎市の総人口、年齢別人口の移り変わりを入力し、グラフとしました。お年寄りの人口比率がここ20年間で6%から15%に増大していることなどを視覚的に理解できました。
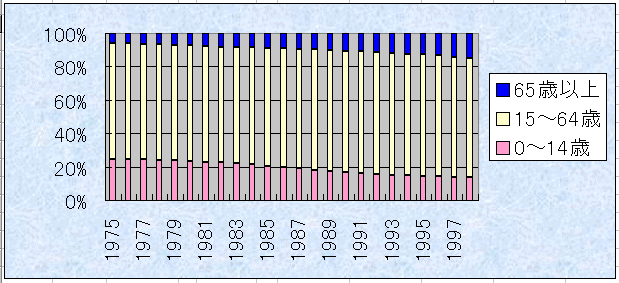
カラーグラデーションやテクスチャの貼り付けなど効果的なプレゼンテーションの手法としての「エクセル」を5時間ほど学習したあと、課題として自分で用意した数字化されたデータをプレゼンテーションとして作成する課題を出しました。データの多数回計算や、ソート、平均、種々のグラフ描写が瞬時にできることに、生徒たちは計算機としてのコンピュータの威力、そのプログラムを創り出す技術者のすごさに感じ入っていました。
3学期、とうとう全員必修の授業最後となりました。予定では「花子」を使った中級CGの学習でしたが、創造性をより発揮できるものとして、「Gifアニメーションで動く画像を作ろう」をテーマとしました。多彩な動きをするサンプルを見せ、ひとりひとり作ってもらうことにしました。これまで言ってきた集大成として、(1)オリジナルな発想であること、キラッと光る何かがあること、(2)行き当たりばったりではなく、渡された設計図に予め概略を書いてから作業を始めることの二つを強調しました。320名の作成したGifアニメーションは実に多彩で感心するものが多くありました。(3)「絵が動いたりするとたのしいし、わくわくするし、それを自分で作ることの楽しさはたまらなかった。」
一番人気のあった課題でした。
3.「情報類型」を選んだ87人のわが愛弟子たち
5つの課題それぞれにアンケートをとりました。
年間平均すると、やさしかった(24%)、どちらともいえない(19%)、むずかしかった(57%)でした。
週1時間の授業で1テーマ数時間で作品を仕上げていくにはやはり6割の生徒が難しかったと答えています。
しかし同時にとったアンケートでは、楽しかった(68%)、どちらともいえない(29%)、楽しくなかった(3%)でした。実に7割の生徒が楽しかったと回答しています。いまどき、全員の7割の生徒が「楽しい」と言う授業は貴重です。
わたしたちは「やさしい=楽しい」と勘違いしがちですが、生徒たちは「難しいけれど楽しい」と言ってくれています。新課程カリキュラムの出発としての「情報基礎1年必修」は、<学びたい>を基本にすえることで学習の可能性を示し、私達を大いに励ましてくれました。
1学年は年間を通し、土曜日の4時限目、「類型ガイダンス」を実施してきました。新課程のねらいや、4類型の概要説明、2年次からの大幅な選択科目の説明などを行いました。
私達は当初、「人文社会3クラス、国際文化3クラス、自然科学1クラス、情報科学1クラス」を想定していました。ところが、7月の調査では「情報科学119人(3クラス)、人文社会95人(2.5クラス)、自然科学66人(1.5クラス)、国際文化33人(1クラス弱)」となりました。種々の討議の中で、<学びたい>を基本とするなら、生徒の気持ちに添った編成をしようと決意を固めました。
最終的に324名のうち、転出1,退学3、留級4、計316名が進級し、2000年4月、「人文社会132人(3クラス強)、情報科学87人(2クラス強)、自然科学65人(1.5クラス)、国際文化34人(1クラス弱)」となりました。
「情報科学類型」を選んだ87人の我が愛弟子たちの構成は実に様々です。
進路希望別に言えば、4年制または短大進学3割、コンピュータ関連専門学校へ進学3割、コンピュータ関連以外の専門学校へ進学2割、就職希望2割です。
学年末の英数国の評価平均は学年平均5.8のところを5.0とかなり低めです。基礎学力不足は痛いところですが、2・3年で全授業の1/3にあたる類型選択の時間を、「むずかしいけど楽しい」からとコンピュータ関連の授業を選択した我が愛弟子たちです。なんとしても生き生きとした学習生活を送らせたいと思います。
4.新課程2年目、類型選択「情報処理」の授業
2年次の「情報科学類型選択」では、授業は週3時間に増えます。
1学期前半「エクセル中級 資格を取る」として、9月24日に実施される「全国商業高等学校協会主催 コンピュータ利用技術検定試験3級」合格を頭において授業しました。
さまざまな関数式、画面飾り、グラフ手法を教え、模擬試験も行いました。意欲的な取り組みが多く見られ、また教えあいなども同じ類型選択という同志感からか多く見られました。
途中、「電子メールウィルスILoveYou」についても擬似的マクロを組み込んでびっくりさせ、仕組みを教え、インターネットに潜む危険さを伝えました。そのことから、担当で話し合い、マクロプログラミングVBAに挑戦しました。犬やネコの絵をクリックすると鳴き声がする、ボタンクリックで2枚目のシートにジャンプする2つのマクロをシートに埋め込みました。最初に「ワンワン」と鳴き声がしたとき、「私にもできるはず」と勢い込んで作業が進みます。「wav」が「wev」となっていてはプログラムは動かないことをお互いで学んでいます。
9/24の試験には、「コンピュータ利用技術検定試験」に23名が受験することとなり、夏休み中冷房のないコンピュータ室で補習・自習しています。
1学期後半は「マルティメディアに挑戦」です。
まず「3DCG」を取り上げることとしました。市販の3DCGソフトウェア40台分の予算(100万円以上)はとてもでそうにありませんので、フリーウェアに頼ることとしました。多くのプログラムを試用してみましたが、使いこなせるものに会えませんでした。
3次元的なものの見方をつかむこと、3次元のカメラ目線を身につけることに目標をしぼることとし、DOGAL1(ドーガレッスン1)というフリーソフトウェア(4)を使わせていただくこととしました。
用意されている3Dの部品を組み合わせて飛行体を作り、空間を飛ぶ軌跡、カメラ目線、背景選択を一人一人設計し、87個の3Dアニメーション作品が出来上がりました。いずれも100フレーム3秒の長さで、mpg圧縮すると
600KB ほどの動画ムービが出来上がりました。
1枚のFDに入りますので、家族・親戚・友人にどこかの機械で見せるよう、それぞれ持って帰ってもらい、喜んでもらいました。恒例となりました全員の鑑賞会では、同じツールを使っても、ここまで「個性が違う」ことにびっくりしています。「自分を表現する」ツールとしてコンピュータがあることがよく伝わるようになりました。
次にこうした「創作ムービ」に背景音楽をいれるためのMidiを学びました。作曲のための和音の基礎を音楽科より教えていただき、自動的に和音伴奏が入るフリーソフト「作曲支援アプリケーション れっつめろめろ
A_Composition.exe」を使わせていただきました。
ソフトウェアの力で自動的に和音伴奏附きでできあがったものを、Midi譜面に移して自分の感じにあうように作り直したものです。バンドをやっている生徒、ピアノを引く生徒、吹奏楽部員には、直接Midi編曲ソフトを使って作曲して良いこととしました。
「明るい曲」「テンポの早い曲」「落ち着いた曲」「楽器に工夫した曲」など多彩な創作曲ができあがりました。
5.あと1年半が楽しみです
実はこの4類型選択は1年の10月に最終決定をします。決めがたい事を早い時期に決定するわけで、類型授業が始まっている今、生徒たちがどうとらえているか不安でもありました。
6月に全員アンケートを取り、「自分の類型を選んで正解でしたか?」を問いました。
「選んで良かった(50%)」「他を選べば良かった(9%)」「どちらともいえない(41%)」でした。とりあえずほっとしました。
実際、一斉授業から分かれて類型選択授業を受けるとき、集まるメンバーは「同じ志を持つ者」としての集団です。2年次の情報のように週3時間かなり高度の内容で授業が進みます。それなりに楽しみにして集まってくれます。
いよいよ、<学びたい>を基本として編成した新カリキュラムの最終成否は、週14時間にもわたる3年次の「類型選択授業」をどう準備するかにかかってきました。
2学期、情報の授業では、音入りの「創作ムービー」を制作することとしています。サンプル模倣、設計、静止画像複数作成、アニメーション動画構成、音入れ、編集エフェクト、試写会、という手順で作業し、それぞれで用いるフリーウェア群の試用がだいたい終わりました。夏休みの課題として、「設計」「静止画像試作」を出してあります。家庭にコンピュータのない生徒が半数いますから、夏休み1週間、午後4時間、部屋のコンピュータを自分のものとして使って良いという「使用願い」を出したうえの自由使用をつきあいました。友達といっしょに20人ほどが暑い夏、課題を仕上げていきました。
1学期の授業の感想として、いろいろな声が聞こえています。
「1年のときよりも、授業の時間が増えていいと思った。あと、1年の時の授業は、何かむずかしいと思うのがそんなになくて、少し物足りないかなと思っていましたが、2年の授業はむずかしいので、よいと思います。」
「難しくってついていけない。いつもとなりの友達がしてくれている。でも本当は自分ですごくやりたい。回りがみんな早いからすごくアセる。」
「はっきり言って、ついていかれへん。自分が情報えらんだのは間違った選択をしたのかなと思う。しかし選んだ以上はがんばっていきます。」
「色々と先生方には欠席とか遅刻とか迷惑をかけたけど、それなりに授業は楽しかった。色々と勉強にもなったし、今度お金がたまったらコンピュータを買おうとも思っているところだった。なにかと便利だから。これからは遅刻も欠席もなくしてぞんぶんに情報の勉強を楽しもうとおもっています。これからもヨロシク。」
「1年の時より、情報がおもしろくなってきたところです。いろいろなコンピュータのしくみがわかってきたり、いろんなことにチャレンジをしていっているのがたのしいです。これから、どんなことをやっていくのかが楽しみです。」
楽しみにしてくれている生徒たちと、あと1年半、色々なことができそうです。
「創作ムービー制作」「ワープロ中級」「パワーポイントプレゼンテーション」「HTML中級」「VBプログラミング」「商業デザイン・情報管理などの商業科目」、「各種資格試験挑戦」・・・。準備するがわも大変ですが、それとても生徒たちのうれしそうな顔が見られるのであればなんでもやってみようと思えます。
コンピュータ室が1室ではとうてい足りなくなること、
ソフト購入費用がでそうにないこと、
担当教員の2名増など
条件整備には種々の困難がありますが、2年前「予算とひとのない」ところで始めようとした「新課程」です。
教員間で討議しながらすすめていくことで前進できると確信しています。
2000.8.15
|

