平安神宮のにぎわい |
|
 朝11時でしたがもうたくさんの人出でした。車のナンバーも東京や神奈川からでした。忙しく巫女さんが立ち働いていました。
朝11時でしたがもうたくさんの人出でした。車のナンバーも東京や神奈川からでした。忙しく巫女さんが立ち働いていました。沿道にはテキ屋さんのたこ焼き・イカ焼き・ねぎ焼きなどたくさんの出店が並んでいました。お昼御飯のかわりにいろいろ買って、3人でパクパク。高いのですが、それが出店の人たちの年間収入のかなりの部分だと聞きます。 気付くことは着物が少ないことでした。関西近縁から着付けをして出てくるにはもう少しあとの時間なのでしょうが、夕方までどこでもそんなに見かけませんでした。 なにか変わってきているのでしょう。 |
|
地域に根付く神社仏閣 |
|

|

|
|
ホテルのすぐ横に岡崎神社がありました。近くの方々が連れ立ってお参りに来ていました。 新年のあいさつをかわし、かしわ手を打つさまが京都に住む人たちの生活に根付いているのだと感じられました。 このあと下鴨神社に久しぶりにお参りしてきました。糺(ただす)の森といううっそうとした森の中の神社です。ここも普段着を着た人たちでいっぱいでした。中には干支ごとの小さなほこらがあり、それぞれの干支に従って今年1年の安寧を祈ります。 |
|
今年の運勢は? |
|
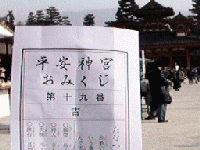 |

|
|
不思議ですが、神社へ行くと「おみくじ」を引いてしまいます。まず竹のジャラジャラから棒を引いて番号を読み、その番号を巫女さんに告げるとその番号の札を渡されます。100円であったり300円であったりします。 50番ほどの番号があり、その番号を告げると、巫女さんが札番号の引き出しから札を取り出します。自分の運勢が50ほどの組み合わせの中のひとつであるはずがないとおもいながらも、でたのが「吉」だったりすると、なんだか安心してしまいます。 |
|
次代へ継いでいく文化遺産 |
|
 キンピカの金閣寺を家族に見せたくて、洛西へ行って来ました。足利義満の栄華のあととはいえ、広大な敷地をわがものとする権力の常に改めて目をみはります。
キンピカの金閣寺を家族に見せたくて、洛西へ行って来ました。足利義満の栄華のあととはいえ、広大な敷地をわがものとする権力の常に改めて目をみはります。しかし戦乱に苦しむ庶民からいえばキンピカの仏堂が極楽へ導くものとしてありがたいとこれに願いを託したと思います。今は古仏として美術品とみられる、古都の仏像はそのすべてがキンピカの信仰対象であったわけで、そのことをもういちど考える時期に来ているのだろうと思います。 |
|
尼崎への帰り道、東寺へよりました。ここの五重の塔は、江戸寛永時代の建立で350年たっています。現存する日本の古い塔の中で最高の高さ57mだそうです。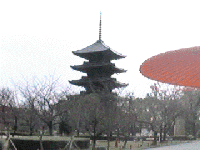 弘法大師の創建(826年)以後、4回の戦火焼失を受けてます。 弘法大師の創建(826年)以後、4回の戦火焼失を受けてます。もう二度と戦火では焼失させないと、次代に決意することは、多くの文化遺産を次代に伝える責務を負っているわたしたちおとなとしてどうしてもやりとおさねばならないことです。 それとともに父母の国たる中国、姉兄たる朝鮮、民族を同じくするアジアの人々とまっとうに手をたずさえていくには、歴史をまっとうに見て、次代の青年にまっとうに伝える細かい日常の作業が、今こそ必要とされているときはないように思います。 |
|
ではみなさん、2000年をあと2年にひかえた本年、いい年でありますよう。 |
|
 「季節散策」目次へ
「季節散策」目次へ